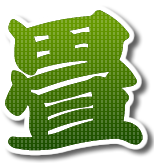琉球表に関して詳しく解説します👩🎓
意味と特徴
琉球表は、琉球産の灯心草(りゅうきゅうい)を素材にして作られます。
麻糸を縦にし、シチトウ(七島)の茎を横にして織った畳表です。
丈夫で耐久性があり、荷物の上包みにも利用されます。
琉球藺(い)や青表(アオオモテ)とも呼ばれ、柔道場の畳や庶民の莚(むしろ)、茣蓙(ござ)に広く使われています。
歴史と現在
琉球藺は、古くはユウナ(オオハマボウ)の樹皮から得られる繊維糸で織られていました。
現在では琉球藺はあまり栽培されておらず、合成繊維製の莚(むしろ)が普及しています。
沖縄では1960年代まで盛んに栽培されていましたが、現在は大分県でわずかに栽培されている程度です。
Q価格の安い中国産の琉球表について教えてください
中国産の琉球表については、価格や特徴を以下に詳しく説明します。
価格
中国産の琉球表は、国産品に比べてリーズナブルな価格で提供されています。価格は畳サイズや素材、仕様によって異なりますが、一般的な半畳サイズの琉球畳は約15000円からあります。
2025年10月の時点では入手が困難になっております。
素材と品質
中国産の琉球表は、い草や和紙、化学素材などを使用して作られています。
琉球表の原料である七島イ草は、国産品と比べて希少で価格が高いため、中国産の畳はリーズナブルな代替品として人気です。
ただし、い草でつくられた琉球表は、縁のない部分が傷みやすいことに注意が必要です。
耐久性
琉球表は一般的な畳と同様に、耐久性があります。
縁無し半畳サイズの琉球表でも、和紙や化学素材を選ぶことで耐久性を重視できます。
Q・琉球表のデメリットメリットを教えてください
メリット
耐久性
琉球表は柔道場などで使われるほど耐久性があります。使えば使うほど良い雰囲気が出てきます。
スタイリッシュな見た目
ゴツゴツとした野性味がある畳表で、スッキリとしたおしゃれな雰囲気を持っています。縁がないため圧迫感がなく、そのためお部屋を広く感じる様にになります。
洋間(フローリング)との相性が良い
縁なし畳として、洋室の一部に取り入れることができます。
デメリット
価格が高い
琉球表(青表)は希少価値が高く、生産者が少ないため価格が高くなります。
琉球表(青表)は販売価格は時価となり予約制の受注生産となります。
出来栄えの差が出やすい
琉球表(青表)は手作業の部分が多く、織ることができる枚数が限られているため、出来上がりの質にばらつきが出ることがあります。
琉球表(青表)は品質のクレームに対応してもらえない。
琉球表の使用感の感想
肌ざわりと風合い
琉球表は少しざらざらした肌触りを持ち、強靭さを感じる特有の風合いがあります。
新品時は草の表面がケバ立ち、ザラザラしていることがありますが、使用するうちに自然に艶が出て味わい深い畳となります。
耐久性と強さ
琉球表は柔道場などで使われるほど耐久性があります。
強い草繊維を使用しているため、長期間の使用にも耐えます。
外観とデザイン
琉球表(青表)は独特の外観を持ち、スッキリとしたおしゃれな雰囲気を醸し出します。
ダイケンの和紙製はカラーバリエーションも豊富で、お部屋の雰囲気に合わせて選べます。
注意点
新品時は毛羽立ちがあるためストッキングが伝線することがありますが、使用するうちに草の表面が擦れて艶が出てきます。
経糸(たていと)の麻糸が表面に出てくることが多いですが、これは自然な現象です。
総じて琉球表は普通の畳とは異なる特性を持ち、その風合いを楽しむ方にお勧めです